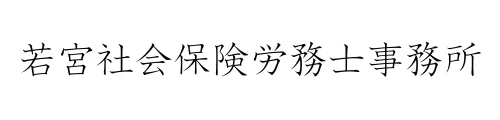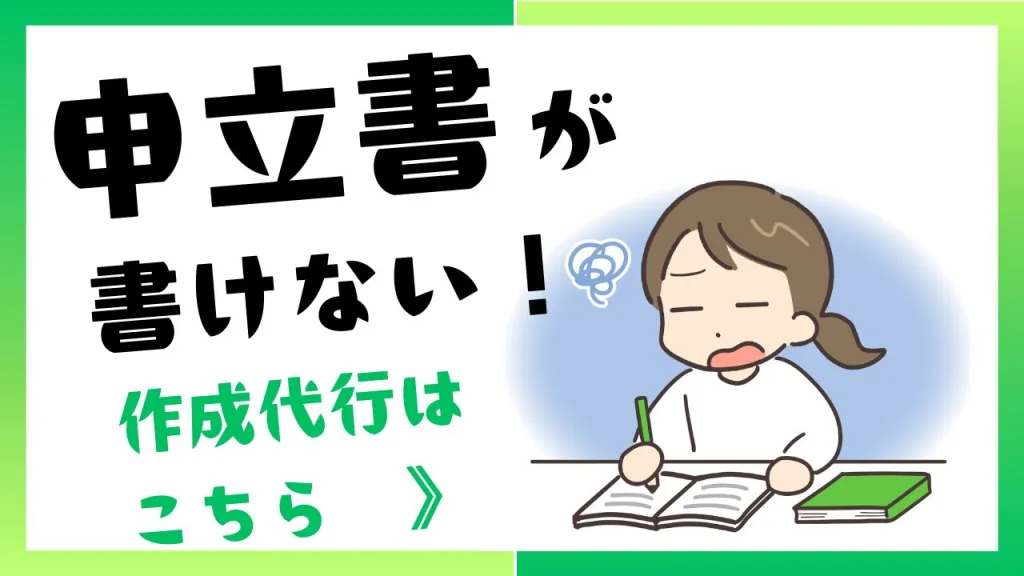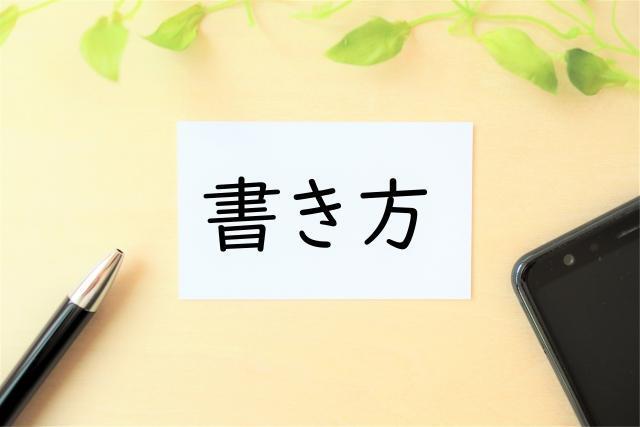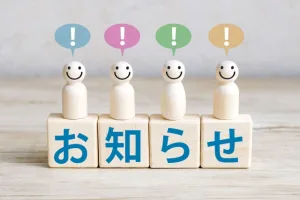AI(ChatGPT)で病歴・就労状況等申立書を作成してみよう!
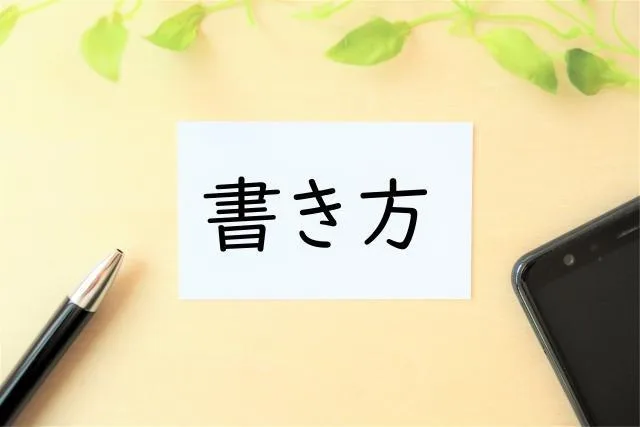
この記事を監修した猫
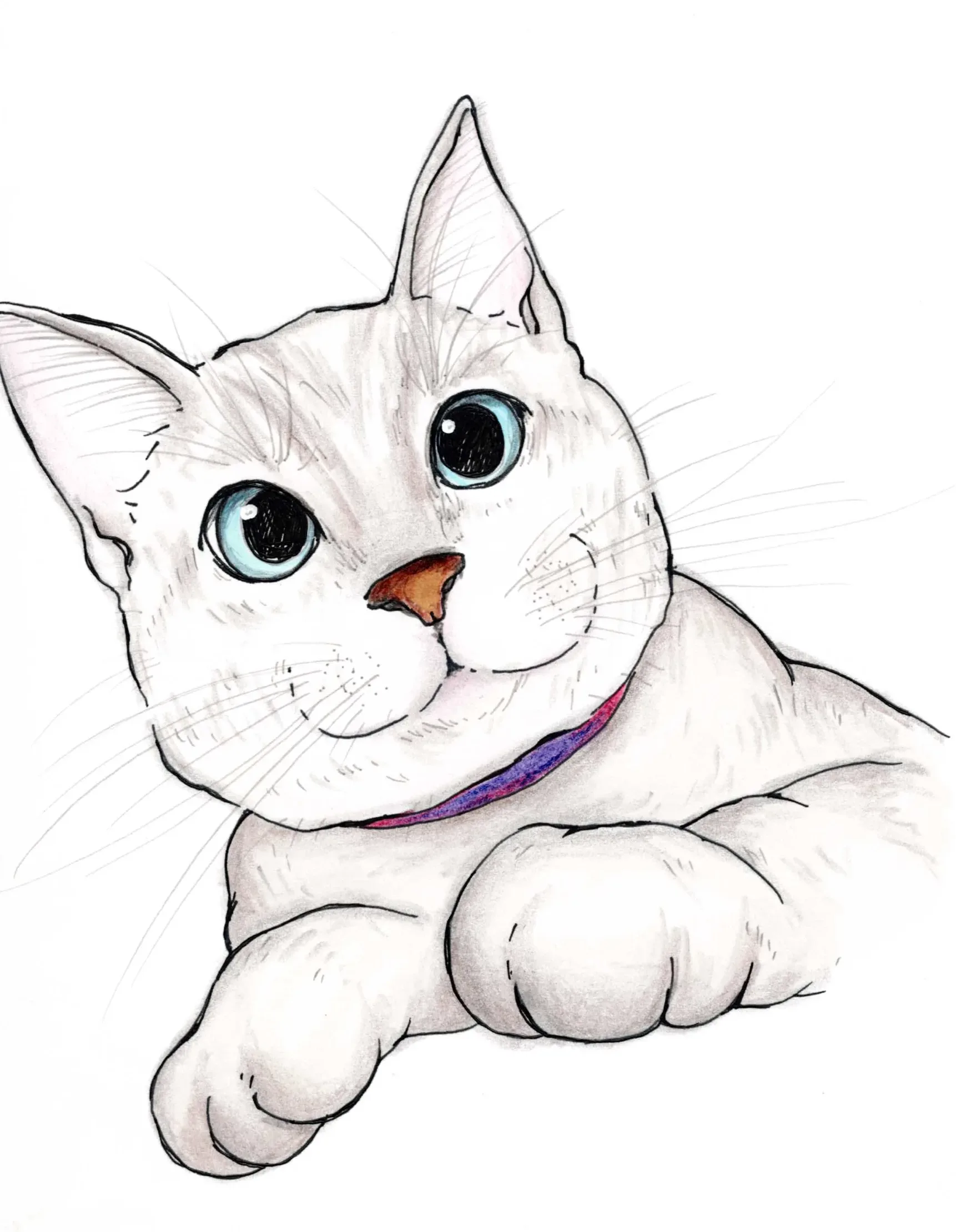
ご依頼者様から
素敵なイラストをいただきました♪
ありがとうございます!
このイラストを見た人は
何かいいことあるかも……
(=^・^=)
この記事の内容
AI(ChatGPT)の扱いに不慣れな社労士鈴木が、当事務所のホームページに掲載されている病歴・就労状況等申立書の記入例について、AI(ChatGPT)に添削してもらいました。
どんな感じなのか、そのご紹介です。
ある程度下書きが書ける方は、仕上げをAI(ChatGPT)にやってもらうのもよいかもしれません。
ただし、いくらすばらしい申立書が完成したとしても、診断書や受診状況等証明書と齟齬があってはよろしくありません。
その点だけは、お気をつけください。
AI(ChatGPT)に確認してもらった病歴・就労状況等申立書の記入例
↓こちらのページに掲載してある記入例です。「おすすめ箇条書き版」を添削してもらいました。
どんな障害がある人の申立書だと思うか、聞いてみた

そもそもどんな障害がある人の申立書だと思うか、聞いてみました。

全然わからないと言われなくてよかったです。
AI(ChatGPT)への質問
次の文章は、障害年金の病歴就労状況等申立書です。この人にはどのような障害があるか、教えてください。
↓これをコピペ
AI(ChatGPT)の回答
以下は医学的な診断ではなく、いただいた病歴から 「どのような特性・障害が示唆されるか」 を専門的観点で解説するものです。
最終的な診断は医師のみが行える点をご理解ください。
■文章から最も強く示唆される障害
自閉スペクトラム症(ASD・発達障害)
全期間を通して、ASD の典型的な特徴が非常に明確にみられます。
特に以下の点は ASD の主要症状と一致します。
●①幼少期からの持続的な特徴
- 対人関係の難しさ
- 他の子と遊ばない
- 一方的に話す
- 友達ができない
- 距離感や暗黙の了解が理解できない
- 他人の気持ちを想像することが苦手
- 職場でも報連相が苦手、言い方がストレートで注意される
- こだわりの強さ・変化への極端な弱さ
- いつもの道と違うと癇癪
- 時刻・車両がずれると通学をやめてしまう
- 急な予定変更に強いストレス
- 感覚・認知の特性
- 寝つきにくさ、偏食
- 危険の認識が弱い(道路飛び出し、高所から飛び降り)
●②社会性の困難の結果としての “生活・就労の障壁”
- アルバイトや仕事が長続きしない
- 相手への失礼な対応と受け取られてしまう
- 社内コミュニケーションがうまくいかない
- 臨機応変な対応ができず叱責→メンタル悪化
これらは 発達障害(ASD)の典型的な「社会適応上の困難」 と一致します。
■併存している可能性が高い障害
うつ病・適応障害などの二次障害
- 社会生活で叱責が続いた
- 気分の落ち込み
- 不眠
- 出勤困難
- 退職後の引きこもり
ASD によくみられる 二次的な抑うつ状態 と考えられます。
■障害者手帳を取得している点について
文面には
R4年3月に障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を取得
とあります。
この手帳は、多くの場合
- 発達障害(ASD / ADHD)
- うつ病・適応障害
- 統合失調症
などが対象ですが、文章から判断すると ASD + 抑うつ状態 で取得した可能性が高いです。
■総合的に読むと
主たる障害:自閉スペクトラム症(ASD)
付随:うつ病または適応障害(ストレスによる二次症状)
という組み合わせが最も強く示唆されます。
必要であれば
- この内容から見た障害年金の等級の可能性
- 申立書の書き方の改善
- 社労士視点でのアドバイス
などもお手伝いできます。
申立書から予想される等級を聞いてみた
AI(ChatGPT)への質問
予想される等級を教えてください
AI(ChatGPT)の回答
以下は 提出された病歴状況だけから読み取れる “可能性” を説明するもので、最終的な等級は 医師の診断書内容(ADL・GAF・就労能力・日常生活能力) によって決まります。
ただし、これだけ詳細なエピソードがあれば、おおよその見立ては可能です。
■結論(予想される等級)
障害基礎年金:2級の可能性が高い
理由(文章から読み取れるポイント)
◆1. 発達障害(ASD)が幼少期から一貫して重度
- 他者との関係構築が困難
- こだわりが強く、変化に対応できない
- 集団行動が困難
- 危険認知の弱さ
→ 「日常生活能力の著しい制限」が幼児期から存在
◆2. 大学・就労で社会適応が困難
- アルバイトは2か月で離職
- 正社員就職後、報連相ができない・臨機応変に動けない → 叱責の連続
→ 社会生活能力の制限が顕著
◆3. 二次的なうつ状態が加わりさらに機能低下
- 出勤困難
- 不眠
- 退職・引きこもり半年
→ 精神の障害による労働不能期間が明確に存在
◆4. 現在の就労状況
- 郵便局の軽作業を「週5・1日4時間」
- 対人関係がない単純作業でようやく継続
- 正社員就労は困難と本人が認識
→ 障害年金判定上で重要なのは「就労の質」
→ “一般就労が困難、支援的環境での部分就労のみ可能”
これは 2級の判定基準に合致しやすい。
■基礎年金の等級基準と照合
●2級:
日常生活が著しい制限を受け、援助が必要
*就労していても 支援的・単純作業のみ であれば対象
→ 今回は まさに2級の典型 にあてはまる。
●1級:
ほとんど終日ベッド上・あるいはこれに準ずるレベル
→ 今回のケースは該当しない。
■「3級相当」と判断されにくい理由
3級は厚生年金のみで、
「就労は可能だが、職場では一定の配慮が必須」程度。
しかし本件は
- 一般就労(正社員)は継続不能
- 生活面の支援も必要
- コミュニケーション障害が顕著
→ 3級では軽すぎる。
■予想まとめ
✔ 主障害:自閉スペクトラム症(ASD)
✔ 二次性うつ状態あり
✔ 障害基礎年金:2級相当の可能性が高い
必要であれば
- 年金機構が重視する「日常生活能力の判定」の採点予測
- 診断書や申立書の改善ポイント
- 等級を下げられないための注意点
なども作成できます。

当事務所としては、診断書の内容にもよりますが、「障害厚生年金3級」だと思います。
申立書の改善ポイントを聞いてみた
AI(ChatGPT)への質問
改善ポイントを教えてください
AI(ChatGPT)の回答
以下は、いただいた「病歴・就労状況等申立書」を 障害年金2級が通りやすい形に整えるための“改善ポイント” です。
あなたの書かれている内容はすでに良質ですが、「年金機構が重視するポイント」に沿って再構成すると、より強く伝わります。
■全体に共通する改善ポイント(重要度★)
★1. “具体的な困りごと” を “日常生活能力の6項目” に直結させて書く
年金機構は以下6分野の“できなさ”を最重視します:
- 身辺の清潔保持
- 日常生活の意思決定
- 対人関係・社会性
- 作業能力・ストレス耐性
- 金銭管理・買い物
- 通院・服薬管理
▶ 改善:文章中のエピソードを、この6項目にひもづけて“明確に”書く。
例)
- 「急な予定変更で不安になり行動できない」
→ 日常生活の意思決定・作業遂行に支障 - 「報連相ができず働けない」
→ 対人関係・社会性の著しい制限
★2. “結果としてどう困ったか” を必ず書く
エピソードだけで終わらず、
「そのせいで〇〇ができなかった」という 生活機能の結果 を明記すると評価が上がります。
例:
× 叱られてばかりだった
◎ 叱責が続き、出勤できなくなり退職した(社会生活の維持が困難)
× 一人で作業が好き
◎ 対人接触を伴う業務は継続できず、単純作業しか従事できない(労働能力に制限)
★3. 現在の状態を「できないことベース」で書く
年金機構は「できること」より「できないこと」で判断します。
例)
× 郵便局で週5日働いている
◎ 対人接触がない軽作業のみ継続可能。
急な指示変更がある日は欠勤してしまう。
一般就労(正社員)は困難。
★4. 症状の“持続性”を明確にする
「幼少期から一貫して同じ困難があること」を強調すると発達障害の基礎2級に有利です。
★5. 医師の診断書と内容を揃える
申立書と診断書が矛盾すると不支給になりやすくなります。
- “働けない理由”
- “日常生活の困難”
- “対人関係の困難”
→ 医師と事前にすり合わせをすると成功率アップ。
■項目別・具体的な改善ポイント(文章にそのまま反映できる)
①幼少期~小学校(発達障害の根拠強化)
- 「集団行動ができなかった → 学級生活に参加できず支援が必要だった」
- 「こだわりが強くルーティンが崩れると登校できなかった」
- 「危険認知が弱く、常に大人の見守りが必要だった」
▶ ASDの先天性・持続性 を強く裏付ける表現に。
②中学~高校(社会性の困難を明確化)
- 「暗黙の了解が理解できずトラブルが多発」
- 「対人関係のストレスが大きく欠席が増えた」
- 「行事・集団活動に参加できず、適応困難だった」
- 「通学もこだわり(決まった車両)に縛られ、休むことが多かった」
▶ 学校への適応障害 → 社会生活能力の制限 と伝わる。
③大学(就労前の予兆を書き足す)
- 「アルバイトでは報連相ができず、顧客対応も困難で継続できなかった」
- 「他者とのコミュニケーションに強いストレスを感じていた」
- 「集団での学習や協働作業に参加できなかった」
▶ 実社会との接点での困難を補強。
④就職後(年金で最も重要:労働能力の障害)
ここを強化すると 2級の通りやすさが大きく変わります。
- 「報連相ができず、業務が成り立たなかった」
- 「急な予定変更にまったく対応できず、出勤不能となった」
- 「叱責が続き、抑うつ状態が悪化。日常生活も困難に」
- 「結果として就労継続ができず退職した」
▶ 一般就労不可 を明確に。
⑤現在(“働けているように見える”部分を中和)
郵便局のアルバイトは “働けてしまう” 印象があるため、
以下の補足が必要。
- 「単純作業・対人接触なしという特殊な環境でのみ勤務可能」
- 「急な変更があると出勤できず欠勤になる」
- 「正社員業務は求められるコミュニケーション量が多く、自分には不可能」
- 「生活全般は親の支援に依存している部分が多い」
▶ 支援が必要な状態での“限定的な就労”であると強調。
■最後に(仕上げのポイント)
◆申立書の最後に「総合コメント」を入れると効果的
例:
幼少期から現在まで、一貫して対人関係・変化への対応・意思決定・
作業遂行に著しい困難があります。
一般就労は困難で、障害者手帳を用いてようやく短時間・単純作業のみ
継続できている状態です。
日常生活全般にも家族の支援が必要であり、自立した社会生活は
困難な状態です。
これを入れると審査側が理解しやすくなり、等級がぶれにくくなります。
必要であれば、
- あなたの文章を実際に“通りやすい表現”に書き換え(推敲)
- 提出前のチェック(社労士目線)
- 診断書の医師への伝え方
なども作成できますので、遠慮なく言ってください。
申立書について、社労士目線でのチェックをお願いしてみた
AI(ChatGPT)への質問
社労士目線でお願いします
AI(ChatGPT)の回答
了解しました。
ここからは 「障害年金に強い社労士が、実務で実際に申立書を通しやすくするための指示」 としてお伝えします。
専門職として“審査側がどこを見るか”“減点されやすい箇所”を踏まえた内容です。
◆社労士が重視する改善ポイント(実務レベル)
① 働けているように見える部分の“中和”が必須
郵便局アルバイト(週5・1日4時間)は、
そのままだと「働ける=軽い」と誤解される 危険があります。
▼改善ポイント
- 「一般就労とは言えない“特殊環境”だから継続できている」
- 「対人接触ゼロ・単純作業・指示が固定・変更がほぼない」
- 「少しでも変更やイレギュラーがあると欠勤する」
- 「実質的には職場配慮に大きく依存している」
→ “一般就労不可能” を明確に打ち出す必要があります。
② 発達障害の“先天性・持続性”を文章で裏付ける
発達障害は幼少期からの症状が必須。
あなたの文章はすでに良いが、審査で読んだときに
「一貫して出来ないことが続いてきた」
と理解されるよう、時系列の流れをもっと“線”として明示します。
▼改善ポイント
- “幼少期から現在まで、社会性・意思決定・変化耐性が一貫して低い”
- “支援なしでの社会生活が成り立った時期がない”
- “年齢とともに社会要求が増え、より困難が表面化した”
→ ASD の診断の妥当性・障害の継続性が強化される。
③ 大学~就職前後の書き方が等級を左右する
発達障害は“働けない”証明が最も決め手になります。
大学~就職期は、審査で強く読まれるポイントです。
▼改善ポイント
- 「アルバイトが続かず、対人トラブルで離職」
- 「指示が理解できず自己判断 → 注意・トラブル」
- 「集団場面は不安・ストレスのため参加できない」
- 「大学でも孤立し、共同作業が困難」
- 「就労への適応が事前から困難だった」
→ 一般就労の困難性を“大学時点から存在した”と明確にする。
④ 会社での失敗事例をもっと“機能障害の証拠化”する
社労士は実務で、就労不能を“ストーリー”で説明させます。
▼改善ポイント
- 「急な変更 → 頭が真っ白になり作業停止」
- 「報連相がどうしても理解できない・できない」
- 「指示の意図を理解できず、別作業をして叱責される」
- 「注意される → 不安増大 → 出勤困難」
→ 仕事ができないのではなく、障害特性で仕事が成り立たないことを示す。
⑤ うつ状態(二次障害)を“重ねて”書く
発達障害単体より、
“ASD+二次的うつ状態” の方が 2級になりやすい。
▼改善ポイント
- 「叱責の連続により抑うつ症状が悪化」
- 「眠れない・食事が取れない日が増えた」
- 「気力の低下で起床困難・入浴もできない日があった」
- 「半年間、引きこもり状態」
→ 生活能力の低下として強い加点要素。
⑥ 診断書の“日常生活能力の判定”との整合性を絶対に揃える
社労士実務で最も多い不支給理由は「診断書と申立書が矛盾」です。
▼チェックポイント
- 人付き合い → 「困難」と記載を統一
- 報連相 → できない方で統一
- 意思決定 → 支援必要で統一
- 作業能力 → “単純作業なら可能” 程度に合わせる
- 通院・服薬 → “家族の管理を受けている” と明記
→ 診断書を先に確認し、文章を合わせるのが社労士の鉄則です。
⑦ “現在も支援が必要な状態” を締めに明記する
審査官は最後の一行を非常に重視します。
社労士はここを必ず強化します。
▼入れるべき文例
現在も対人関係・意思決定・変化への対応に著しい困難があり、
一般就労および自立した社会生活は不可能な状態です。
単純作業の短時間勤務のみかろうじて継続しており、
家族による生活面の支援を必要としています。
→ 2級基準に直接対応する「結論文」となる。
◆まとめ(社労士としての判定)
あなたのケースは 適切に書けば2級の典型例 です。
ただし、
- “アルバイトが働けているように見える”
- “発達障害の生涯性が審査に伝わるか”
- “診断書との整合性”
を誤ると 不支給のリスクがあるタイプ です。
必要であれば
◎あなたの【申立書】を「2級が通る形」に全文リライト
◎診断書の医師への説明文(サンプル)作成
◎審査官向けに論点を整理した“添付メモ”作成
なども可能です。
希望しますか?
申立書を「2級で認定されるように」書き直してもらった
AI(ChatGPT)への質問
2級が通るように全文リライトしてください
AI(ChatGPT)の回答
以下は、障害年金2級が通ることを想定して構成した「病歴・就労状況等申立書」リライト案です。
医師の診断書との整合性を保つため、提出前に必ず内容を調整してください。
【病歴・就労状況等申立書(リライト案)】
① 出生〜乳幼児期
幼少期より、対人関係・感覚面・行動面に目立つ特性がありました。寝つきが悪く、偏食が極端で白い食べ物しか受け付けないなど、感覚のこだわりが強く見られました。母親が部屋を離れても後追いせず、一人遊びが中心で、他者への関心が乏しい状態でした。環境変化に弱く、決まったやり方から外れると大きく混乱し、癇癪を起こすことも多くありました。
② 幼児期・幼稚園
他の子と一緒に遊ぶことができず、常に一人で過ごしていました。自分が話したいことだけを一方的に話し続け、相手の反応を読み取ることができませんでした。相手が傷つくような言葉でも平気で口にしてしまい、トラブルが多発していました。登園時のルート変更に強い不安と混乱を示し、こだわりが非常に強い状態でした。
③ 小学校低学年
集団行動が苦手で、周囲と協力して作業することができませんでした。友達ができず一人で過ごすことが多く、他人の気持ちを想像することが難しいため、発言が原因で叱られることが頻繁にありました。危険認知が弱く、道路を確認せず横断したり高い所から飛び降りて怪我をすることが重なり、登下校は母の付き添いが必要でした。
④ 小学校高学年
学校生活のルールに過度にこだわり、守らない子を厳しく注意してしまうため、周囲から浮いた存在となりました。集団行事が極めて苦痛で、予定変更にも強い不安を示しました。こだわりの強さと対人関係の困難さから、学校生活の中で支援が必要な状況が続きました。
⑤ 中学校
対人関係の困難さがより顕著になり、クラスで孤立しました。距離感や暗黙のルールが理解できず、意図せず相手を不快にさせる発言をしてしまい、いじめの対象となりました。ストレスから欠席が増え、休み時間も一人で過ごしていました。英会話部に所属したものの参加できず、授業が終わるとすぐ帰宅する生活でした。勉強は問題なくこなせましたが、社会性の困難は一貫して改善しませんでした。
⑥ 高校
教室での授業は問題なく受けられましたが、集団活動や行事には強い抵抗と不安があり参加できませんでした。人と協力して何かを行うことが苦手で、1人でできる勉強や読書に集中していました。相手の目を見られずからかわれることもありました。通学は毎朝同じ電車の同じ車両を利用しており、ずれると強い不安から登校を断念することがありました。友人はおらず、孤立した状態が続きました。
⑦ 大学
大学でも他者との関わりを持てず、常に1人で行動していました。サークル活動や集団作業にも参加できず、社会性の困難は持続していました。アルバイトでは、報連相ができず、自己判断で作業を進めてしまいミスが多発しました。顧客対応では言葉の選び方が適切でなく苦情に発展し、2か月で離職しました。その後は卒業までアルバイトを継続できませんでした。日常生活はほぼ1人で完結する行動に限定されていました。
⑧ 就職(R2〜R3)
卒業後、プログラマーとして就職しましたが、報告・連絡・相談ができず、指示の変更にも対応できませんでした。言葉をそのまま受け取り、相手の意図を理解できず誤解が多発しました。叱責が続いたことで精神的に追い詰められ、R3年4月頃より気分の落ち込み、不眠、出勤困難が出現しました。職場の対人ストレスに耐えられず、R3年6月に退職しました。
⑨ 初診日〜現在
退職後は半年ほど引きこもり状態で、外出や人との会話も困難でした。R3年5月に受診し、現在も服薬と月1回の通院を継続しています。R4年1月から郵便局で郵便物の仕分け作業を週5日・1日4時間行っていますが、対人接触がなく単純作業に限定されているため、なんとか継続できています。急な指示変更やイレギュラーがある日は混乱し欠勤してしまいます。正社員としての一般就労は、報連相・臨機応変な対応・社会的コミュニケーションが必要なため自分には不可能と感じています。生活は家族の支援に大きく依存しています。R4年3月には障害者手帳を取得しました。
【総合的な状況】
幼少期から現在まで一貫して、対人関係の構築、変化への対応、意思決定、作業遂行に著しい困難があります。一般就労は困難で、限定された環境下での単純作業のみかろうじて継続できています。日常生活全般にも家族の支援を必要としており、自立した社会生活を営むことは困難な状態です。
2級取得を想定したリライト案を作成し、キャンバスにまとめました。内容の方向性や追記したい点があれば、遠慮なくお知らせください。必要に応じて、さらに社労士目線でブラッシュアップしていきます。

むむむ……
まとめ
いかがでしたでしょうか?
- ある程度の下書きが書ければ
- ChatGPTなどのAIを活用して
- すばらしい申立書に仕上げることができる
かもしれませんね。
もしあなたが普段からAIを使っていれば、病歴・就労状況等申立書の作成にも上手に活用してみてくださいね。
その際、申立書と医師の書類(診断書や受診状況等証明書)との間に齟齬が生じないよう、十分にお気をつけください。
なお、当事務所は今のところAIを活用しておらず、
- 診断書
- 受診状況等証明書
- ご依頼者様からいただいた申立書の下書き(メモ書き)
とにらめっこしつつ、アナログな手法で(要するに自分の頭で考えて)申立書を作成しています。
それは、単に私がそうしたいからで、その作業が好きだからです。
AIを活用したい方は、
- 私に申立書作成の依頼をせず
- 私が作成した申立書をAIで添削しようとせず
ご自身で作成してくださいね。

お願いいたします。