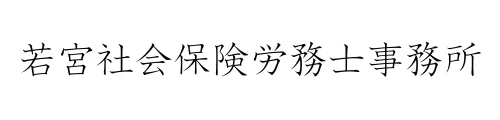審査請求・不服申立|精神の障害年金で審査結果に納得できない?
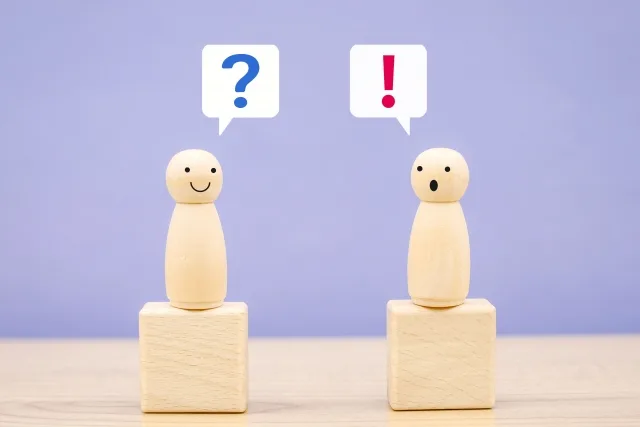
この記事の内容
この記事では、「障害の状態による不支給決定」や、「想定よりも低い等級での支給決定」がなされたときの、その結果の受け止め方について考えてみます。
結論としては、例外はあるにせよ、本人が納得できる・できないに関係なく、妥当な決定であることがほとんどだということです。
そのため、誰がどう見ても首をかしげるような決定なら話は別ですが、そうではない場合、感情的にむやみやたらと審査請求に進んでも時間とエネルギーの無駄遣いです。
勢いで不服申立てをするのではなく、冷静に結果を分析してみましょう。
その際、もしご自身での判断が難しければ、社労士に相談してみるのもよいでしょう。
精神的なつらさ≠障害の重さ
客観的事実が重要
少なくとも、精神の障害年金においては、「精神的なつらさ」と「障害の重さ」はイコールではありません。
障害年金請求では、「(気持ちが)つらいか・つらくないか」ではなく、「(実際に)できるのか・できないのか」が重要です。
そして、「(実際に)できる・できない」は、主観ではなく客観的事実で判断されます。
客観的事実とは、この場合、「診断書の記載内容」や「就労の有無(厚生年金の加入記録)」、あるいは「同居家族(援助者)の有無」などです。
主観的な「つらさ」は関係ない
たとえば、あなたがどれほどつらい思いをしていようが、診断書の記載内容が認定基準に該当しなければ、障害年金は支給されません。
あるいは、あなたがどれほど長い年月つらい思いに耐えてきたとしても、就労して厚生年金に安定的に加入していた期間が長ければ、遡及請求は認められないかもしれません。
つまり、あなたの障害の状態に関する事実は、あなたの内面にあるわけではないのです。
それは、「診断書」や「厚生年金の加入歴」、あるいは「援助者の有無」等の客観的事実の中にのみ存在します。
また、たしかに「障害年金は診断書次第」なのかもしれませんが、それは「診断書ウラ面の日常生活状況についてどこにマルを付けてもらうか」という意味ではありません。
それは、「あなたの障害の状態に関する事実は、あなたの内面的つらさと関係なく、診断書に明記されている」という意味です。
不支給だったとき or 2級を狙ったのに3級だったとき
ショックは大きいが冷静に
社労士に依頼せずにご自身で請求した場合、想定した結果にならなかったときのショックは特に大きいものがあるだろうと思います。
社労士に依頼すれば、依頼時や請求時にある程度の見通しは教えてもらえるため、それなりの心構えができます。
しかし、ご自身で請求する場合は、事前の情報がなくいきなり結果を突き付けられるため、余計にショックが大きくなってしまうのでしょう。
その際、感情的に次の一手を打とうとする前に、下記のようなことについてちょっと冷静に考えてみていただきたいと思います。
提出した書類の内容こそが「事実」
すでに記したように、あなたの障害の状態に関する事実は、あなたの内面的つらさと関係なく、診断書に明記されています。
これはつまり、「たしかに診断書は提出したが、事実は違う。実際にはもっと症状が重いし、もっと状態が悪い。」という主張は通用しないということです。
なぜなら、提出した書類の内容こそが「実際」であり、「事実」だからです。
自分で「これが事実です」と提出した書類について、「それは事実と違う」と自分で不服を申し立てても、道理に合いません。
診断書の内容が事実と違うと思えば、請求書類の提出前に、診断書を書いた医師に対して意見を述べなければならなかったのです。
不服申立てとは、「診断書にはこう書いてあるけど、実際の私の状態はもっと悪いんです」と申し立てるものではありません。
そうではなく、「事実を適正に反映した提出書類の内容が正当に評価されていないことについて」不服を申し立てるものです。
だからこそ、最初の請求の際、「いかに事実をきちんと反映させた書類を準備するか」、あるいは、「提出書類にいかに事実を反映させるか」が重要なのです。
書類の提出後に悪化した場合の不服申し立ては無意味
「請求書類を提出した時点と比べ、今の状態はかなり悪化している」というような場合、不服申立ては意味がありません。
先に述べたように、不服申立てとは、「提出書類の内容が正当に評価されていない」ことについて行うものです。
よって、そもそも提出書類の内容が現在の状態(事実)と違うのであれば、不服申立ては成り立ちません。それならば現在の状態がわかる書類をもう一度提出してくれということになります。
そのような場合は、不服申立てではなく、裁定請求を再度行う(再裁定請求)ということになるでしょう。
ただ、再度の診断書作成を医師に依頼しても、医師が医学的判断としてその悪化をどのように捉えるのかが重要です。
仮に一過性のものとして処方薬の調整等で様子を見るということであれば、すぐに新しい診断書を書いてくれることはないかもしれません。
また、もしもすぐに新しい診断書を書いてくれたとしても、今度は審査側に不信感を与えてしまい、カルテを提出するよう指示が出るかもしれません。
いずれにせよ、医師と十分に相談する必要があるでしょう。
遡及請求が認められなかったとき
請求すれば認定されるわけではない
遡及請求をした場合、それが認められるかどうかは非常に大きな関心事でしょう。
認められれば、初回支給額が数百万円になるからです。
そのため、これが不支給であったときのショックも、とても大きなものとなります。
ですが、当然のことながら、請求すれば必ず認定されるものではありません。
診断書だけで決まるわけではない
遡及請求の難しさは、「その後の経過」がわかってしまっていることです。
たとえ障害認定日時点の診断書が認定基準に該当するものであり、現在の診断書も同様なものであったとしても、それだけで支給認定されるわけではありません。
たとえば、10年前の障害認定日時点で重い障害の状態にあり、その診断書を取得できたとします。そして、現在も同様の状態で同様の診断書を取得できたとします。
でも、これだけで遡及請求が支給認定されるわけではありません。
ずっと認定基準に該当するような障害の状態でしたか?
もちろん、障害認定日以降現在まで重い障害の状態が継続していれば、そのときは遡及請求が認められる可能性が高いと言えます。
しかし、たとえば、認定日以降現在までの10年間のうち7年間は一般就労できており、厚生年金にも加入していたという場合はどうでしょうか?
おそらく、遡及請求が認められることはないでしょう。
遡及請求が認められるということは、仮に障害認定日が10年前だったとすれば、本来はこの10年分の障害年金が遡って支給されるということです(時効があるため、実際には直近5年分しか支給されませんが)。
ということは、この10年間、ずっと認定基準に該当するような障害の状態にあったということです。
ところが、うち7年間を厚生年金に加入して一般就労できていたとすれば、とても「この10年間、ずっと認定基準に該当するような障害の状態にあった」と言うことはできないでしょう。
ガイドラインを過信しない
上記のように、「その後の経過」がわかってしまっている遡及請求においては、ただ「診断書の内容が認定基準に該当する」というだけでは、支給認定されることが難しくなります。
遡及が認められるかどうかは支給額的に大問題であるため、「等級判定ガイドラインの表に当てはめれば認められるはずなのに、不支給なんておかしい!不服申立てだ!」となる気持ちも理解できます。
ただ、ガイドラインの目安はあくまでも目安であり、それ以上でもそれ以下でもありません。
これは遡及請求に限らないことですが、ガイドラインの表だけを意識するのではなく、落ち着いて判断するようにしましょう。
審査請求を社労士に依頼する前に考えるべきこと
着手金について考えてみる
「自分でやってみてダメだった。でも、審査請求・再審査請求でチャンスはあと2回ある…よし、じゃあ社労士に依頼してみよう!」と考える人は結構多くいらっしゃると思います。
でも、ちょっと待ってください。
不服申立て(審査請求・再審査請求)を社労士に依頼するとすれば、多くの場合55,000円程度の「着手金」が必要です。
審査請求が認められずに再審査請求までやれば、さらに55,000円が必要です。
これはつまり、社労士としてみれば、その審査請求・再審査請求が通る通らないに関係なく、依頼を受けさえすれば11万円は売り上げがあがるということです。
落ち着いて冷静に考えよう
あくまで仮定の話ですが、もしも障害年金の請求サポートを単にお金儲けの手段と考える社労士がいた場合、その社労士にとって審査請求の依頼ほど簡単な仕事はありません。
依頼を受けた時点で55,000円は入金されるのですから、その審査請求が通る通らないに関係なく、とりあえず形だけの書類を提出すればそれでよいわけです(そもそも通らないのが当たり前ですし)。
そして、当然その審査請求は通りませんので、再審査請求を勧め、もう一度55,000円をゲットするということもできなくはないのです。
おそらく、こんなことを考える社労士はいないはずですが、万が一ということもあります。
不服申立てを検討する際は十分に気を付け、冷静さを失わないようにしましょう。
おわりに
障害年金は、初診日を証明でき、納付要件を満たしていれば、あとは認定基準に該当する状態にある人がきちんと書類をそろえて提出すれば、当然に支給されます。
不支給決定や想定よりも低い等級で決定されるにはそれなりの理由があり、ほとんどは妥当な決定です。
ただ、ときには誰がどう見てもおかしいと思える決定がなされることがあり、そのときにはきちんと不服を申し立てればよいのです。
しかし、ただ「納得できない」「自分のつらさが伝わっていない」という思いだけで不服申立てに進んでも、結果はくつがえらないでしょう。
たとえば、「必死の思いで、胃の痛みと吐き気に耐えながら、地を這うようにして毎日出勤している(していた)」というような場合、障害年金の審査で最も重視されるのは「毎日出勤している(していた)」という事実です。
そこでは、「必死の思い」は考慮されないものと考えておいた方がよいでしょう。
この記事を書いた人

鈴木雅人
| 事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |
| 代表者 | 鈴木雅人 |
| 所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |
| 電話番号 | 080-7712-2518 |
| メール | info@wakamiya-sr.com |
| 定休日 | 不定休 |
| 対応地域 | 全国 |
| 対応方法 | メール/電話/郵送 |
この記事を監修した猫
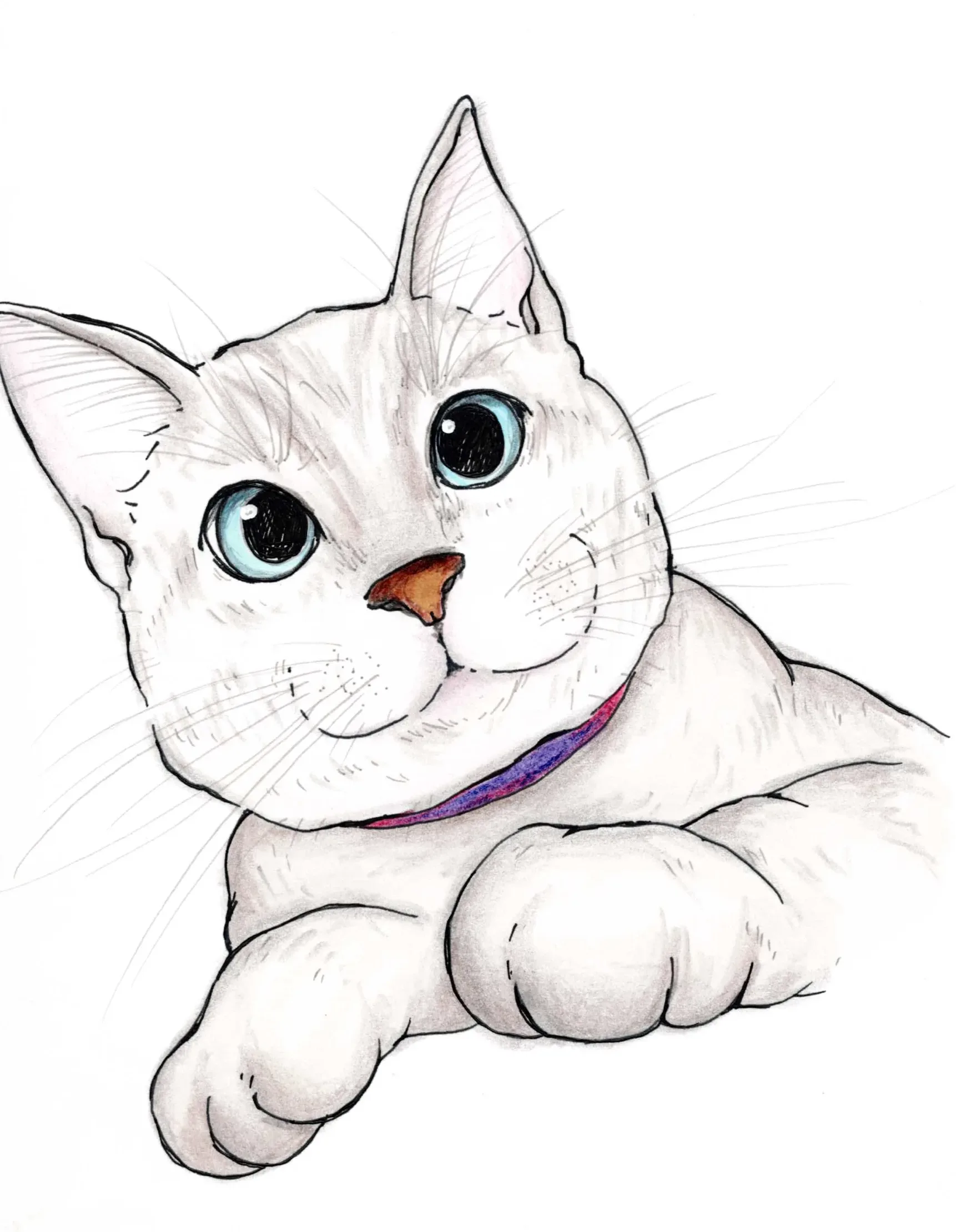
ご依頼者様から
素敵なイラストをいただきました♪
ありがとうございます!
このイラストを見た人は
何かいいことあるかも……
(=^・^=)