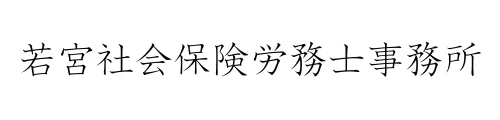この記事の内容
就労(仕事)をしていても障害年金はもらえるのでしょうか?
その答えは、YESでもありNOでもあります。
簡単に言えば、外部障害ならYES、精神障害や内部障害であれば、状況によりYESでもありNOでもあるということになります。
もくじ
原則、障害年金に所得制限はない
障害年金は、ケガや病気により障害の状態となったときのための所得補償制度です。
そのため、「何らかの所得があれば支給されない」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、これは誤ったイメージです。
一部の例外(「20歳前傷病による障害基礎年金」)はあるものの、障害年金の受給に所得制限はなく、受給要件を満たせば誰でも受給できるものです。
働いていたら障害年金はもらえない?
一概には言えない
障害年金の受給可否と収入の有無は、基本的には関係ありません。
では、仕事をして収入を得ている場合はどうでしょうか?
この場合、受給できるともできないとも、一概には言えないことになります。
障害状態該当要件との関連
障害年金と就労の関係において、仕事で得ている収入の多い少ないは、基本的には関係ありません。
では、何が関係あるのでしょうか?
関係があるのは、「仕事をしている」という事実が、受給要件の一つである「障害状態該当要件」を判定するにあたり、どのように判断されるのかという点です。
つまり、「仕事ができる=障害の状態が軽い」と判断される場合があるということです。
影響することあればしないこともある
では、どのような障害でも、仕事をしていれば状態が軽いと判断されてしまうのでしょうか?
そうではありません。
ここで混乱を招きやすいのは、仕事をしていることが受給の可否に与える影響が、障害の種類によって大きく異なるという点です。
障害の種類によって、仕事をしていることが受給の可否に大いに影響を与えることもあれば、まったく影響せず関係のないこともあるのです。
障害の種類による違い
「精神障害・内部障害」と「外部障害」で違う
では、どのような障害であれば仕事をしていることが関係あり、どのような障害であれば関係ないのでしょうか?
基本的に、精神障害と内部障害では大いに関係があり、外部障害ではほとんど関係がないということになります。
内部障害と精神障害の場合
内部障害とは、内科的疾患による障害のことで、つまり「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の第1章第10節~第18節に示されている「呼吸器疾患による障害」、「心疾患による障害」、「腎疾患による障害」、「肝疾患による障害」、「血液・造血器疾患による障害」、「代謝疾患による障害」、「悪性新生物による障害」、「高血圧症による障害」、「その他の疾患による障害」のことです。
精神障害もそうですが、これらの内部障害では、その認定において、就労の有無を含む日常生活状況が重要な判定要素とされています。
外部障害の場合
これに対し、外部障害では、仕事をしているかどうかはほとんど、あるいはまったく認定に影響を与えません。
外部障害とは、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の第1章第1節~第7節に示されている「眼の障害」、「聴覚の障害」、「鼻腔機能の障害」、「平衡機能の障害」、「そしゃく・嚥下機能の障害」、「音声又は言語機能の障害」、「肢体の障害」のことです。
認定基準に違いがある
同じ障害年金であるのに、障害の種類によってこのような差があることは不公平なようにも思えますが、この障害の種類による違いは、それぞれの認定基準・認定要領の違いによるものです。
精神障害や内部障害では、日常生活状況や検査数値等により「総合的に」判断されるのに対し、外部障害では、検査数値や欠損部位により、比較的明確に基準が定められているのです。
では、「総合的」とはどういうことかというと、それはつまりケースバイケース、個々の状況に応じて、そのときどきで判断するということで、そこに障害年金請求の難しさがあると考えられます。
年金の種類による違い
初診日の時点で厚生年金か国民年金か
ここまで、障害年金の請求において、就労の有無が認定に影響を及ぼすかどうかは、障害の種類によって異なるということを確認しました。
そして、就労の有無は、請求する年金の種類によってもその影響度合いが異なることになります。
請求する年金の種類とは、3級まである厚生年金か、2級までしかない国民年金かということです。
これは、自由にどちらかを選べるというものではありません。
初診日に厚生年金に加入していれば厚生年金(障害厚生年金)、国民年金に加入していれば国民年金(障害基礎年金)を請求することになります。
厚生年金(3級)と基礎年金(2級)
では、3級と2級でどのような違いがあるのでしょうか?
「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」には、「障害の程度」として3級に次の記載があります。
「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
これに対し、同じく2級には次の記載があります。
「日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの」
いかがでしょうか?
就労している状況で障害年金を請求する際、3級まである障害厚生年金と、2級までしかない障害基礎年金とで、受給の難易度に差があることがおわかりいただけると思います。
つまり、障害厚生年金であれば働いていても受給できる余地があるものの、障害基礎年金では働いていれば受給の余地はないものと読み取れます。
労働とは「安定した就労」
しかしながら、ひと口に「労働」といっても、そこには様々な働き方があるのもまた事実です。
週5日のフルタイム勤務、パート、アルバイト、障害者雇用、福祉的就労など、それらを十把一絡げにして「労働」とするのもずいぶん雑なまとめ方のように思えます。
実際のところ、ここでいう「労働」とは、「安定した就労」のことを意味しています。
では、「安定した就労」とはどのようなものなのでしょうか?
安定した就労とは
だいたい2年が目安とされる模様
だいたいの目安としては、同じ会社において、休職・欠勤・遅刻・早退等なく、2年以上フルタイム勤務を続けられているような状態です。
たしかに、このような状態であれば、障害要件を満たしていないと判断されても納得できます。
配慮や支援をアピール
逆に、職場の配慮を受けながらの勤務である場合や、体調に波があり休職と復職を繰り返しているような場合は、安定した就労とは言えません。
安定した就労とは言えないのであれば、それだけ障害年金を受給できる可能性が高まるということです。
そのため、もし働きながら障害年金を請求するのであれば、職場で受けている配慮や支援等についてしっかりとアピールし、安定した就労ではないことを正確にわかりやすく主張することが必要となるのです。
受給していても、働き始めたら支給停止?
次の更新までは支給される
では、すでに障害年金を受給している人が、状態が良くなり働き始めた場合はどうなるでしょうか。
すぐに支給が停止されてしまうのでしょうか?
決してそのようなことはありません。
最低でも、次の更新時期までは支給されます。
よって、以下のようなものは、誤ったイメージと言えます。
誤ったイメージ
- 「就労=障害状態の改善」と必ずみなされる
- 働き始めたら、すぐに支給停止となる
- 働くか障害年金を受給するか、どちらかを選ばなければならない
つまり、支給停止になるのは、更新時に「安定した就労」ができていると判断された場合です。
アルバイトなどで少しずつ働き始めたとしても、それですぐに支給停止になるわけではありません。
勤務形態等を考慮し、個々に判断されるのです。
職場での援助や配慮があれば、診断書に記載してもらおう
「働くことができる」とひとことで言っても、そこには雇用形態の違いや職場での配慮の有無等、人それぞれに違いがあります。
そのため、一概に「働いているからダメ」ということにはなりません。
新規の請求手続き/更新手続きに関係なく、実際の就労状況を医師に伝え、職場での配慮等について診断書に記載してもらうようにしましょう。
関連記事
🔗障害年金の等級を知るには診断書のどこを見ればよいのか(精神の障害用) (wakamiya-sr.com)
🔗認定基準(精神の障害) (wakamiya-sr.com)
🔗精神障害・発達障害で障害年金を申請するときの注意点 (wakamiya-sr.com)
この記事を書いた人

鈴木雅人
| 事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |
| 代表者 | 鈴木雅人 |
| 所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |
| 電話番号 | 080-7712-2518 |
| メール | info@wakamiya-sr.com |
| 定休日 | 不定休 |
| 対応地域 | 全国 |
| 対応方法 | メール/電話/郵送 |
この記事を監修した猫
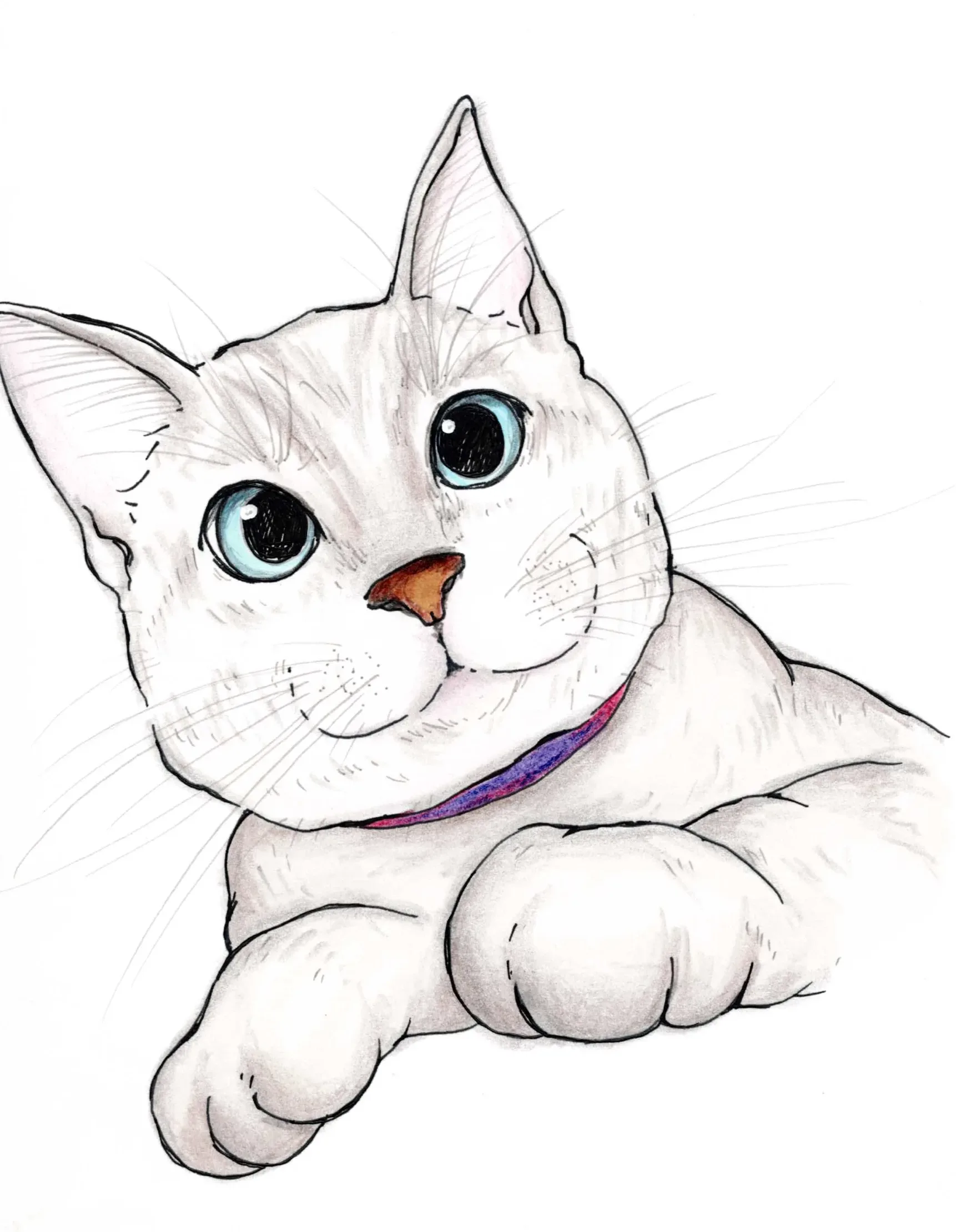
ご依頼者様から
素敵なイラストをいただきました♪
ありがとうございます!
このイラストを見た人は
何かいいことあるかも……
(=^・^=)